▲楽天PR+本文からいくつか引用+感想等で構成されております▲
早速ですが、引用。本文、最後の最後の1文です。
では皆さん、現場で会いましょう。
…え?私に…言ってる?
私、大学卒業して公立小学校音楽専科教諭になって、11年目の研修も終えたあと、夫の海外赴任に帯同するために教員を辞めた人でしてね…
上海とシンガポールの帯同を終えて、さぁ本帰国したからには仕事はどうするか…半年たってやっと仕事を探し始めて、決まったのは週に3回くらいの「飲食店のアルバイト」(しかも1日4時間程度だし、ちょっと会話しただけで採用っていう…偶然ただの人手不足だから即採用って感じも)
教員現役の友達からも「どこも人手不足だから、学校はどこでも即採用だよ、きっと」って聞いているのになぜ、教育関係の仕事に戻らなかったか。
それは、教員時代の美しいままの記憶を壊したくない、そんな思いがありまして。
『教員働かせ放題』なんてワードまで生まれてしまうほど、ハードな(ブラックな?)仕事のイメージである教員。もちろん楽しい・美しいことだけだった訳じゃないし、やっぱり大変だったけど、子ども達との美しい記憶の方が強いと言う幸せ。
教員時代、ちょくちょく校長先生と担任の先生を呼んでの「音楽室発表会」をしていたのですが、その時の子ども達の音を合わせようとする真剣な表情…発表を終えて、先生方に感想を聞くときのワクワクしている表情…それを見るのが私の幸せでした。全校行事の音楽会も大変だったけど、拍手を受ける子ども達の姿は本当にカッコよかった。子ども達の歌声を聞くのは私にとって何よりの癒しだったし、演奏できなかった部分ができるようになって喜ぶ子どもの姿も本当に魅力的で。そういう美しい場面を、音楽教員としてたくさん見てきました。
そんな美しい思い出ばかりを残している私なのですが、この本の第7章 学校教育が生き残るための新時代の評価ルールの「学校とは人が集まらなければできないことをする場所」の項目の中で著者がこう言っていて…
ダンスの授業では、チームを編成して行うと気持ちがいい。音楽の授業でも、合唱してハモったときの心地よさは格別だ。図工や美術についても、独りでも創作はできるが、隣のクラスメートの進行を覗き見しながら、ときにカンニングしたりパクったりしつつ試行錯誤することが大切だ。
あぁ…👆読んだら…やっぱり教育現場に戻りたくなっちゃったじゃんね!(涙)
正規教員でフルタイムで働く「担任や専科の先生」だけでなく、子ども達との関わり方は様々ある時代(時給制の非常勤講師とか)。
だからこそ、この本と出会って、しかも最後の最後に著者から”現場で会いましょう”なんて言葉を受け取って、なにやら妙に悩んでしまった私なのでした…しかも今のバイトも結構楽しいなんて、幸せな悩みですね。
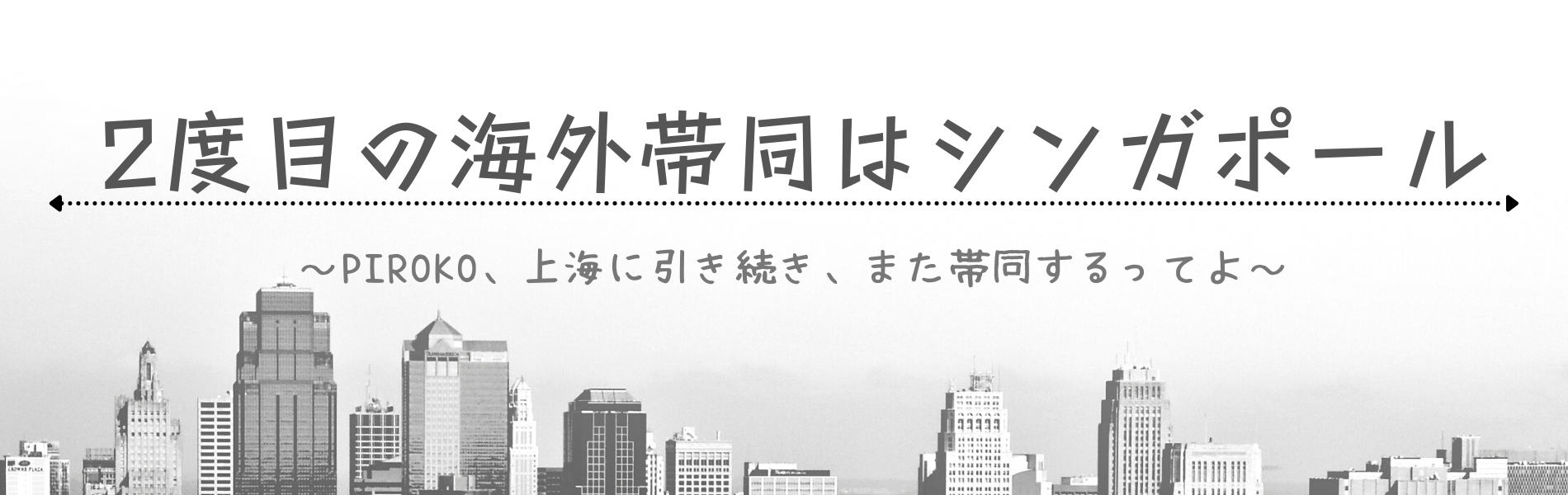
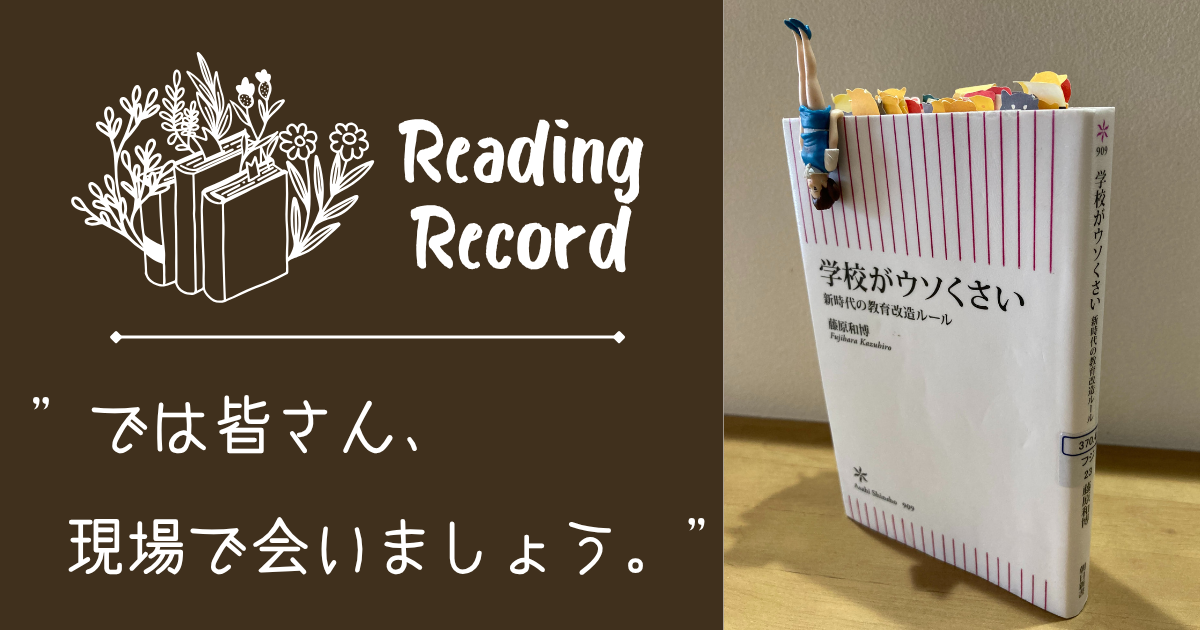
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/494f436e.616c2d91.494f436f.c7bc33c1/?me_id=1213310&item_id=20966643&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fbook%2Fcabinet%2F2196%2F9784022952196_3_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

